街頭配布を“外注する意味”とは?――プロに任せるべき合理的な理由と、よくあるハードルの乗り越え方
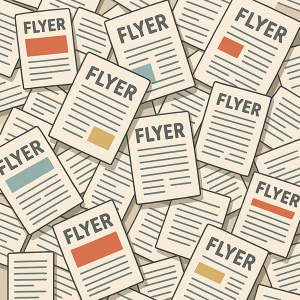
導入:「自分たちでやるのが当たり前」…でも本当にそれでいい?
街頭配布(チラシ配布、ビラ配り、ポケットティッシュ配布)は、リアルな接点をつくるうえで最も基本的かつ重要な販促手法です。
そのため、「自店のスタッフがやるべき」「店長が立ってこそ伝わる」といった考えは、現場・本部問わず強く根付いています。
たしかに、“自分たちの言葉で伝える”という姿勢はとても大事です。
しかし、それだけで本当に「効果的に」「継続的に」「お客様に届く配布」ができているでしょうか?
今回は、あえて外部の配布プロに依頼する合理的な理由と、それに立ちはだかるネック・誤解、そしてその解決法をお伝えします。
あえて「外部プロ」に任せるべき合理的な理由
1. 配布テクニックとデータに基づいた“成果主義”
声かけ・立ち位置・人の流れ・配布物の持ち方など、受取り率を上げるノウハウを熟知しています。
過去の実績データをもとに「どのタイミングで何をどう配れば成果が出るか」を考えて動けるのがプロの強みです。
2. 営業中の人手不足に対応できる
配布に人を割きたくても、「営業しながらは無理…」という現場も多いはず。
外注すれば、ピーク時間中も安定した宣伝活動が継続可能です。複数日・複数拠点など、対応しづらいボリュームにも柔軟に対応できます。
3. ブランドイメージを守る“品のある配布”
服装・表情・言葉づかい。すべてが「企業の顔」となる街頭配布では、配布者のクオリティがブランドを左右します。
自社スタッフでは対応しきれない接客力や所作の細部まで徹底できるのが、プロに頼む安心感です。
4. 結果を分析して、次につなげられる
「配ったけど、どうだった?」が曖昧になりがちな自社実施に対し、外部プロは配布数・反応・動線情報をレポートでフィードバックできます。
これにより、次回以降の販促活動も改善されていきます。
よくある“依頼できない”ネックとは?
1. 「うちの想いはうちの人が伝えないと」の思い込み
本気で接客しているお店ほど、「自分たちの手でやるべき」という想いが強くなります。
ただし、配布=接客ではなく、“きっかけづくり”。
「出会いの最初の一歩を、専門職が最大効率でつくる」と捉える視点が必要です。
2. 「お金がかかる」=費用対効果への不安
人件費や手配料が目に見える分、「高いのでは?」という印象を持たれがちです。
しかし、限られた人員で“配布漏れ”や“質のバラつき”が起こる方が実はロスが大きいケースも。
目に見えない“失われた機会”を見直す視点も必要です。
3. 本部・間接部門が「現場主義」に偏りすぎる
「現場でやってこそ本物」という“現場信仰”が本部にもあると、現場が外部活用を提案しづらくなります。
特に全国チェーンやフランチャイズでは、本部からの方向づけが強く影響します。
ネックをどう乗り越える?――店舗側・本部側、それぞれの解決法
▼ 店舗側への解決アプローチ
- 「店内接客に集中する分、入り口はプロに任せる」という役割分担の提案
- 「1日だけ」「特定エリアだけ」など小規模な外注で効果を体感してもらう
- 店長やスタッフが一緒に立つことでノウハウ共有の場にできることを伝える
▼ 本部・間接部門への解決アプローチ
- 全国で統一的に外注活用できるよう、ガイドラインや推奨業者リストを整備
- 費用対効果の定量データ(受取り率、来店率)をもとにROIで意思決定
- 店舗の負担軽減・販促品質向上の両面から“本部主導の支援策”として設計
まとめ:街頭配布こそ、プロの力を最大限活かす価値がある
街頭配布は“基本”であるがゆえに、誰がやっても同じに見えるかもしれません。
しかし、同じ「配る」でも“成果に直結する配り方”はプロにしかできない領域です。
外部に任せるのは、手を抜くことではありません。
むしろ、「成果を出すために、あえて最適な手段を選ぶ」こと。
せいじつ屋では、単なる“手配”ではなく、店舗様・本部様それぞれと連携し、販促戦略としての街頭配布を一緒に組み立てるご提案をしております。
外部活用に一歩踏み出すきっかけとして、ぜひお気軽にご相談ください。


